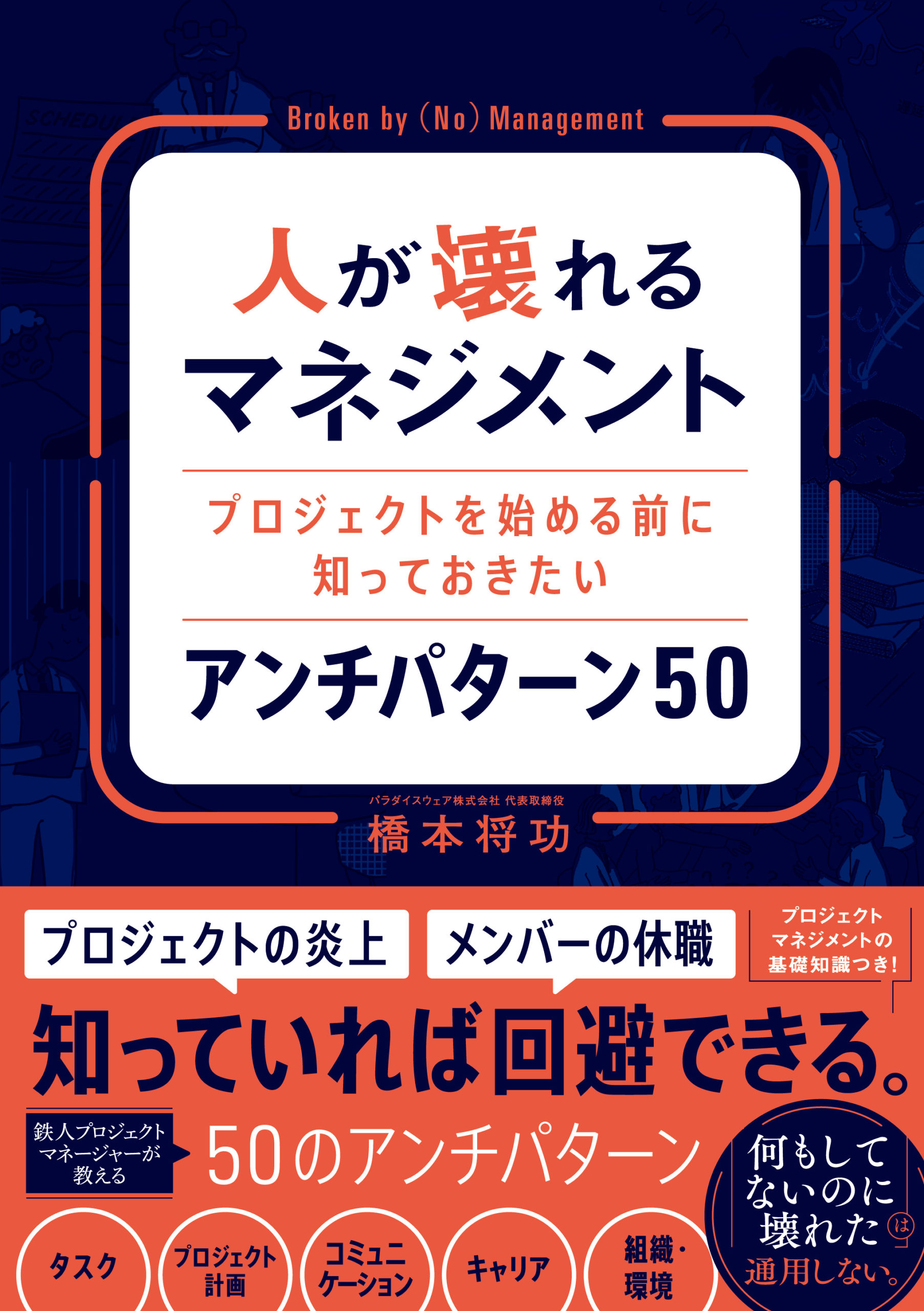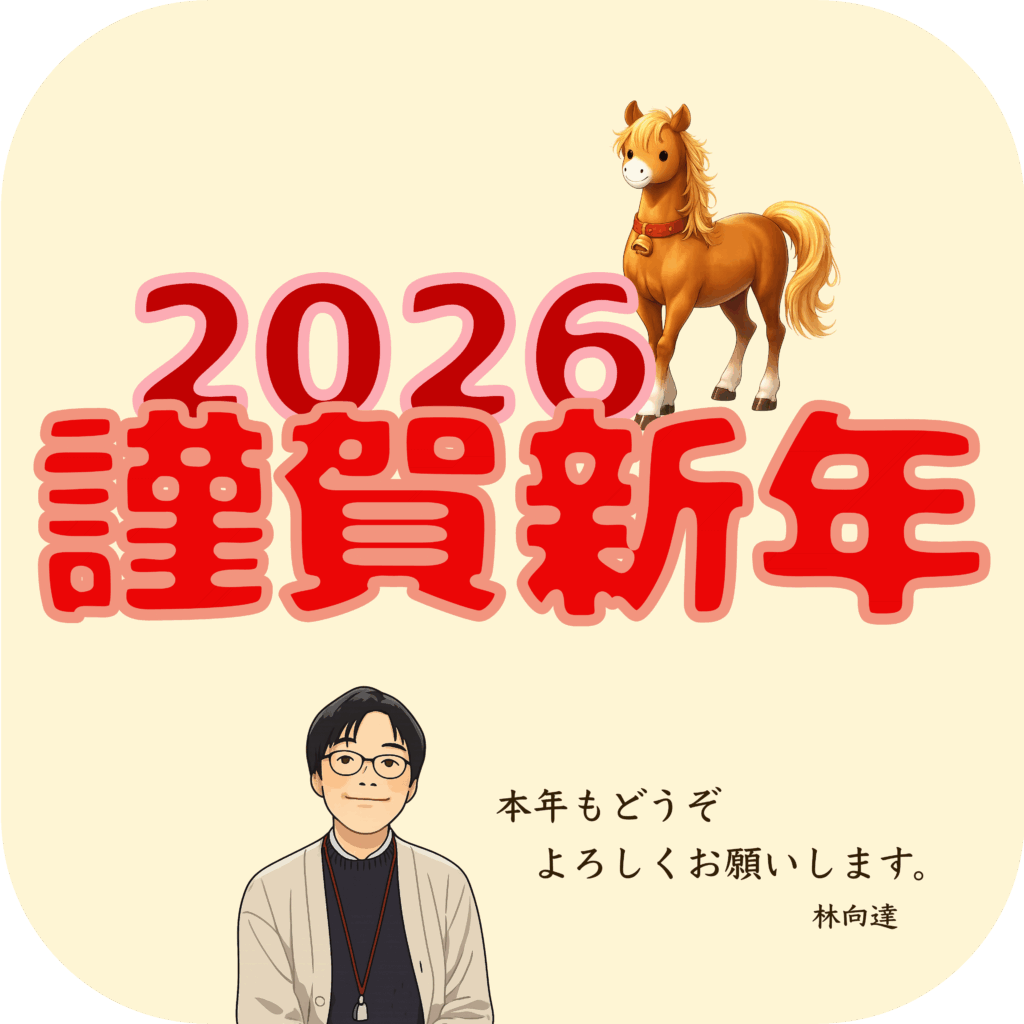
組織の中での成長
組織における教育や学習について研究している人たちが周りにいたこともあって、私自身の専門ではないけれど、わりとずっと気にしてきた。
そうでなくとも、ビジネス書の売れ筋である人材育成の本は、どの書店に寄っても上位ランキング本として目立つ場所に掲げられているので、たまに立ち読みなどする。
残念ながら、私自身は人の上に立った経験がキャリアを通してほとんどない。
唯一、短大教員時代にメディアセンター長なる役職を得て、二人くらいの助手さんの上司になったことが私のマネージャー経験だ。あとはヒラ大学教員が続いたので、上司経験もなければ、部下意識もないまま時が過ぎた。
だから、ビジネス書を自分自身のために読むことはなく、あくまでも教養的に覗き見してきたというのが実際のところだ。
ところが、ここ最近は、そういったビジネス書をずいぶん身近なテーマと感じながら手にすることが多くなってきた。たとえば、この本はあちこちの書店でランキングの棚に並んでいる。
この本の序章「リードマネジメントで組織パフォーマンスを最大化する」はこんな節題が並んでいる。
- なぜ優秀なプレイヤーが優秀なマネージャーになり得ないのか?
- 「私のようになれ」の意識がメンバーたちを苦しめる
- 任せられないマネージャーはメンバーからの不信感を買う
- マネージャーの頭の中だけに存在する「べき論」とサヨナラする
- 今すぐ「マネジメントの無免許運転」から脱却しよう
- 「選択理論心理学」をベースにしたまったく新しいマネジメント手法
- 「人間の行動メカニズム」を考え直すことが勉強のスタート
- リードマネジメント実践のための5つの技術
本の内容予告みたいな後半の節部分はさて置いて、最初のつかみとなる節部分は、ありがちなシチュエーションを的確に捉えている鉄板ネタで読者を引きつける。
そういえば、この類いのアンチパターンを集めた本も最近書店で積まれていた。数打ちゃあたる的にパターンを集めているので少々胃もたれするが、面白い本ではある。
残りの人生で他人の上司になる機会が、あるのかどうか分からないけれども、組織の中で人が成長することを優先できるように、こういった本からいろいろ学んでおきたい。
心は気まぐれ
このブログも一年ほどお休みをした。
昨年度は大学教員から小学校教員へ。今年度からは小中一貫校となったので中学校教育にも関わり始めた。日々の出来事に追われて時間が過ぎている。
何も分からない一年目は自ずと観察して理解に励む日々。とはいえ、傍観しているわけにもいかないから、分からないなりにあれこれ試し続けた。手応えのようなものはまだ築かれていないけれど。
仕事に関する経験値の問題だけでなく、組織という場に対する課題もある。
それまであまり対人関係に煩わされることはなかったが、日常的にたくさんの人々と接し続ける状況では、また違った課題に直面し続ける。こういう状況に対して、社会情動的コンピテンスが求められていることは承知しているが、私たち大人が全員これを育めているとはいえないところに難がある。
さて、私はどうしようか。
着任のご挨拶
2024年4月より瀬戸SOLAN学園初等部(瀬戸SOLAN小学校)に着任しました。
なんと、大学教員から小学校教員への転身となります。そんなことが可能なのか?という皆様もいらっしゃると思いますが、ユニークな私立小学校ということもあって、加えていただきました。
それに、わたくし、休眠した小学校教諭第一種免許の所持者でありますので、それほど無理筋ではない転職かなと思います。(まぁ、大学教員辞めて小学校教員になりたいかどうかは人それぞれですが。)
瀬戸SOLAN小学校は2024年度で4年目に入る愛知県の私立初等部で、2025年度には中等部を設置することになっている小中併設の学園となります。これからさらに変化発展していく学園ですし、それゆえ新陳代謝も激しくはありますが、すべて子どもたちの学びにフォーカスするための過程。私もまた、その変化発展に貢献すべく、一員として尽力したいと考えています。
とはいえ、私をご存知の皆様は「りんさんが、そんな大人しくしてるわけないじゃない」とニヤニヤされていらっしゃるかも知れません。ん〜、まぁ、とりあえずは職場に慣れてからじゃないとね。少しずつ、あれこれやってみたいと思います。

—
学校名を検索して初めていらっしゃった皆様、こんにちは。
その中には本学児童の保護者の皆様もいらっしゃることかと思いますし、学校に関心がある一般の皆様もいらっしゃると思います。
珍しいキャリアの変わり種教員が加わりますこと、ご不安もあるかと思いますが、あらためてどうぞよろしくお願いします。私は高学年の情報の授業を担当いたします。
学校について根掘りなほり書くことは、当然禁じられておりますので、ご関心があることについて有益な情報提供はできないかも知れませんが、各自の研究活動は奨励されていることだと思いますので、その範疇で何か書いているかも知れません。所詮散らかった私の部屋のような場所ですので、片づけられていない恥ずかしい文章を目にしても、どうぞご容赦ください。
新年度始まり、私たちの職場も児童を迎えるのに慌ただしいです。さて、私も準備準備。
退職のご挨拶
3月末日をもちまして徳島文理大学を退職いたしました。
あらためて、徳島でお世話になった皆様に厚く御礼申し上げます。
大過なく15年間勤め、次に移れるのも周りの皆様のおかげだと思います。
本当にありがとうございました。

徳島学校タブレット問題に関心をお持ちになったついでに訪れた皆様、いらっしゃいませ。
斯様な事情で徳島の出来事について新たな情報発信することが難しくなりますので、最新情報などは別のリソースから得ていただければと思います。
新年度からは新たな場所でスタートを切る予定です。またご報告をします。